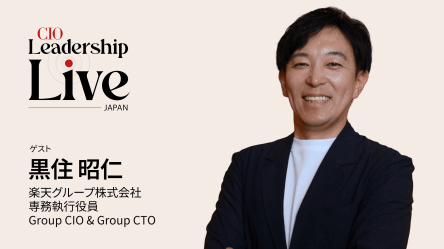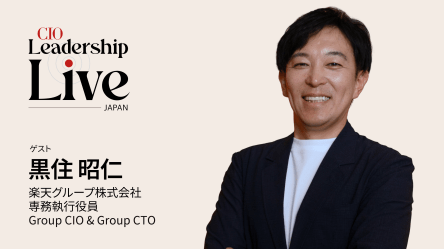かつて「インターネットの次の当たり前」とまで言われたWeb3。しかし、その熱狂はわずか数年で冷め、今では冷静な視線が向けられています。その理由は、単に暗号資産の価格が低迷しているからだけではありません。脆い収益モデル、セキュリティや運営体制の不備、そして直感的に使えないサービスの数々。本稿では、なぜ多くの人が幻滅してしまったのか、その構造的な理由を一つひとつ紐解きながら、Web3が再び歩み出すための条件を探ります。
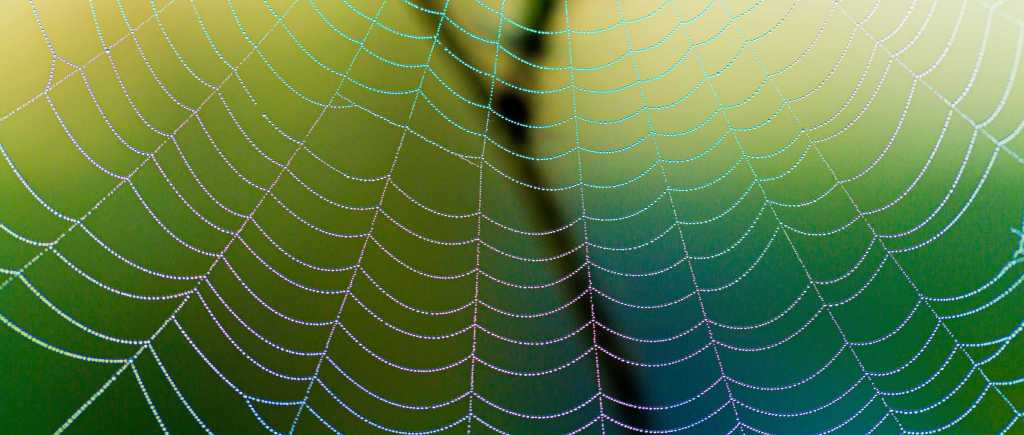
始まりは壮大なビジョン――「デジタル所有」という約束と現実
Web3が最初に抱かせた期待、それは誰もがデジタルデータを真に「所有」し、特定のプラットフォームに縛られることなく自由に持ち運べるという未来像でした。しかし、現実はそう単純ではありません。NFTなどが保証するのは、多くの場合データへの「参照権」のようなもので、著作権や利用許諾といった権利まで自動的に手に入るわけではないのです。例えば、あるゲームのアイテムを別のゲームで使うには、法律上の権利関係と技術的な互換性の両方をクリアしなければなりません。このハードルの高さから、ユーザーが夢見た「どこでも使えるデジタル資産」はごく限られた世界だけのものとなり、多くの人が期待したほどの利便性を感じるには至りませんでした。
ビジョンを歪めた投機熱――「P2E」と二次流通ロイヤリティの限界
こうした壮大なビジョンだけでは、急速な普及は望めませんでした。Web3の熱狂を実際に後押ししたのは、より直接的な「儲かる」というストーリーでした。特に「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」と呼ばれるゲームは、新規参入者が増え続けることとトークン価格の上昇を前提としていたため、成長が止まると経済圏そのものが成り立たなくなります。その設計の脆さは、成長が鈍化するとすぐに露呈しました。
また、NFTの世界では、作品が転売されるたびにクリエイターに収益の一部が還元される「二次流通ロイヤリティ」が期待されていました。しかし、この仕組みはあくまでマーケットプレイス側の自主的な対応に依存しており、強制力がありません。一部の主要なマーケットプレイスがこの方針を転換したことで、ロイヤリティは「約束」から「任意」のものへと変わり、クリエイターが安定収益を見込むのは難しくなりました。
投機マネーの裏で頻発した事故――信頼を蝕んだシステムの脆弱性
投機に依存した脆い経済圏は、技術的なリスクとも隣り合わせでした。異なるブロックチェーン同士を繋ぐ「ブリッジ」は、Web3の利便性を高める上で不可欠な技術ですが、同時にハッキングの格好の標的となります。鍵の管理や検証システムの甘さに加え、問題発生時の対応の遅れが重なり、たった一つの欠陥が巨額の資産流出に繋がる事件が多発しました。
一方で、取引所のような中央集権的なサービスのリスクも浮き彫りになります。ずさんな内部管理や資産管理の不透明さは、多くのユーザーがWeb3を始める際の「入り口」となるサービスへの信頼を根底から揺るがしました。技術的には個人が資産を管理する方が理想的だとしても、現実には多くの人が取引所などに頼らざるを得ない。この矛盾が、理想と現実の溝をさらに深める結果となったのです。
信頼を失わせた「使いづらさ」――複雑な操作と手数料問題
相次ぐ事件はユーザーに不信感を植え付けましたが、それ以前に、Web3には「使いづらい」という根本的な問題がありました。一般のユーザーにとって、秘密鍵やシードフレーズといったパスワードの管理は依然として大きな壁です。たった一度の操作ミスや詐欺で資産を全て失うリスクを個人の注意力に委ねる設計は、日常的に安心して使うことをためらわせます。
さらに、利用者が増えると手数料が高騰し、処理が遅延する問題も普及のボトルネックとなりました。「レイヤー2」と呼ばれる技術の登場でコストは下がりましたが、今度はレイヤー2同士が乱立し、ユーザーはどこに資産を置くべきかという新たな悩みを抱えることになりました。結果として、Web3を意識せずに使えるほどサービスが洗練されるには、まだ時間がかかりそうです。
理念とはかけ離れた実態――見せかけの「分散化」
こうした「使いづらさ」は、皮肉にもWeb3が掲げる「分散化」という理念そのものを揺るがす事態を招きました。多くのユーザーが複雑な操作を避けるために特定の便利なサービスに頼った結果、インフラが一部に集中してしまったのです。ある一つのサービスが停止すると多数のアプリが一斉に利用できなくなる事態は、理想と実態のギャップを浮き彫りにしました。運営方針を決める「ガバナンス」においても、トークンを多く持つ人ほど発言権が強くなる仕組みは資本の集中と表裏一体であり、形だけの分散化が、実質的には一部の権力者に支配されやすいという現実を示しています。
逆風となった外部環境――不透明な規制と市場の変化
Web3がこうした内部的な課題を抱える中、外部環境も厳しさを増していきました。国や地域によって法整備のスピードや内容が異なることは、事業の見通しを立てにくくし、スタートアップにとっては開発コストの増大に繋がりました。
時を同じくして、生成AIが新たな技術トレンドとして大きな期待を集め、資金も優秀な人材もそちらへ流れていきます。投資マネーの流入を前提に事業を拡大してきたWeb3プロジェクトの多くは、この変化に対応できず、プロダクトそのものの価値が厳しく問われる時代へと移り変わったのです。
指標が示す数字の裏側と、大手企業の撤退
このような状況下で、Web3の活況を示すとされたデータにも厳しい目が向けられるようになりました。例えば「アクティブウォレット数」は、無料トークン配布などを狙った自動プログラムによって水増しされているケースが多く、実際のユーザー数を正確に反映しているとは限りません。
こうした実態が明らかになるにつれ、Web3に参入した大手企業も距離を置き始めます。NFT関連サービスの停止や縮小が相次いだことは、一般ユーザーがWeb3に触れる機会が減ったことを象徴する出来事でした。私たちの生活の中に自然に溶け込むような使い道を見つけられなければ、一時的な話題性だけではサービスを維持できない。この厳しい現実が、Web3の熱狂に終止符を打ったのです。
まとめ:熱狂の終わりから、価値創造の始まりへ
Web3への幻滅は、単一の原因によってもたらされたわけではありません。壮大なビジョンと現実のギャップ、投機に依存した脆い経済、相次ぐセキュリティ事故、そして多くの人がついていけない「使いづらさ」。これらの内部的な課題が山積する中で、規制の不透明化やAIへの市場の関心の移行といった外部の逆風が重なり、熱狂は急速に冷めていきました。
しかし、この幻滅の時期は、Web3が次のステップへ進むために不可欠な「踊り場」と捉えることもできます。投機の熱が冷めた今だからこそ、一時的な利益ではなく、真にユーザーのためになる価値とは何かを問い直す機会が訪れたのです。
これまでの失敗から学び、セキュリティを大前提とした上で、誰もが直感的に使えるサービスを生み出すこと。そして、「分散化」という理念を形骸化させるのではなく、そのメリットをユーザーが実感できる形で提供すること。Web3が再び多くの人を惹きつけるには、こうした地道な価値創造の積み重ねが不可欠です。熱狂の終わりは、新たな始まりの合図なのかもしれません。